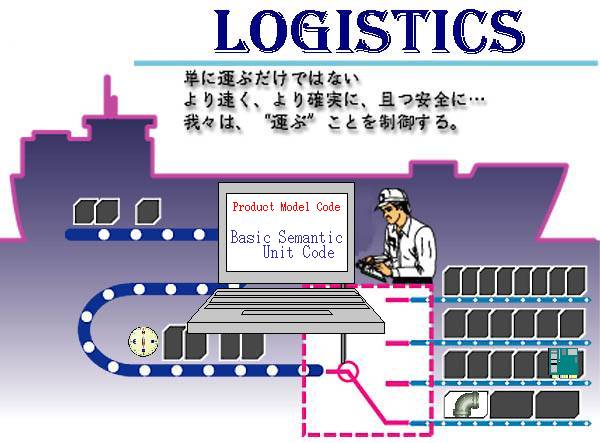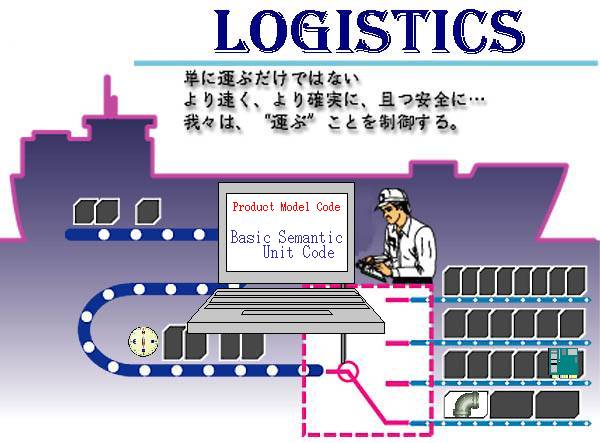|
1)従来の発想にとらわれない柔軟な発想
企業の恒久的テーマである市場ニーズを掴み、産業と社会に貢献するには従来の活動理念にとらわれない柔軟な発想が必要不可欠です。発想の改革が今まさに切望されています。
従来の成功パターンが機能していない代表的要素には、市場のグローバル化による、情報流通についていけていないことが考えられます。
従来構築された、情報流通機構では、市場ニーズに対応する情報リソースの情報共有を確立することができません。
これらの問題を解決するには共有情報リソース(ISO 13584 Plib)の確立が不可欠となります。
また、それらを具現化された姿として、ここに情報コラボレーションを提唱するものです。 |
|
2)当社が発想する情報コラボレーションとは
当社では情報共有に貢献するにはどうすればいいのか、という自問自答を続けています。
情報を共有することとは、一対Nとの共通の認識を生じさせることが目的であり、個別情報においても認識の共有化が可能となることを、意味します。
目指すものは、一つの製品に関わる全て部品、ユニット、製品の情報を有し、情報共有企業としての情報コラボレーションの実現に他なりません。 |
3)情報コラボレーションの構築
物作りを業とする製造業に従事している協力企業として、IT化を推進し、付加価値としての製品情報を提供し、
業務の円滑な推進を目指します。
付加価値としての製品情報を提供することにより、有益な情報が循環されるようになります。
情報コラボレーションを構築することは
―――――――――――――新規事業の創生に他ならないのです。
|
4)新規事業の創生とは
客観的な事例として標準情報化モデルの構築を推進します。(標準テンプレート、標準用語辞書、標準製品クラス辞書、標準付帯参照辞書)
従来資産としてのリソースである人・物・金に加え、情報という資産を考えています。
従来資産に情報という資産を加えることにより、意思決定体制が構築できます。
情報を素早く改廃することにより事業の効率化が可能になります。
―――――――――――――新規事業すなわち、ビジネスモデルの構築なのです。 |
5)情報ビジネスモデルの構築
情報ビジネスモデルを構築するのには、グローバルゼーション化そのものに対応することであり、それらが示唆する対象となる事柄は、ISO,IEC,CALSが提唱している国際規格を、どのように取り込み、システム化し、運用するかが情報ビジネスモデルであって、これらを如何に素早く実行に移すかが現状の課題であります。
|